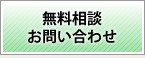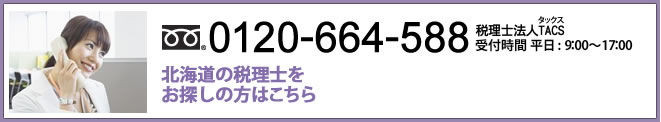贈与したはずが相続財産に!?
相続税対策として生前贈与を行う、という話は以前からよく聞きます。
先般の相続税法改正により相続税の申告が必要となる方が増加すると想定されますので、今後ますます相続税対策の必要性が高まると思われます。
ところが、その贈与が認められずに相続財産とみなされ相続税が課税される場合があります。
例えば、親が子名義で預金通帳を作り、子のためにその通帳に預金をするというケースがあります。
しかし、
(1)子供はその預金の存在を知らない
(2)預金通帳や印鑑は親が管理
といった場合は、その子名義の預金は贈与として認められず、全て親の相続財産とみなされる可能性が高いです。
贈与とは、「あげます」「はい、いただきます」という双方合意の契約であるため、(1)の状態では受け取る側の合意がなく、贈与自体が成立していないと考えられます。
また、贈与だと認めてもらうには、もらった人が自由に使える状態にすることが必要となります。
(2)の状態では受け取る側である子が実質的にその財産を自由に使えないため、贈与とみなされません。
なお、このような預金は『名義預金』と呼ばれています。
※名義預金とは?
形式的には家族の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、
つまりそれら親族の名義を借りているに過ぎない預金のこと。
贈与を行う場合には、間違いなく贈与を行ったという客観的な証拠を残すことが重要となります。
次に掲げるような対応をしておくと有効かと思われます。
①贈与する人の銀行口座から贈与する現金を引出し、もらう人の銀行口座へ毎年あげたい時に
振り込む。
②もらう人は自分名義の口座を作る。
※開設申し込みは必ず本人又は親権者(未成年者の場合)の自署押印であること
③もらった人又はその親権者が通帳・印鑑・証書などを保管する。届出印鑑は必ず贈与者のものと
は別にしておく。
④もらった金額が年間110万円を超える時や相続時精算課税での贈与を選択した場合は必ず
贈与税の申告をする。
⑤贈与をする際には贈与契約書を作成し、確実性を高める場合には確定日付をとっておく。
※『確定日付』とは?
その日に書類が存在していたことを証明するもので、公証役場において有料(1件700
円)で付与されます。
贈与自体は口頭でも成立します。ですがせっかく行った贈与が後になって認められないという事態を避けるためにも、少々手間はかかりますが確実に書面で証拠を残すことをお勧めします。
新着情報
- 2018.08.30
- 事業承継税制と株式の担保提供
- 2018.08.01
- 特例事業承継税制
- 2018.05.25
- 生命保険契約に関する権利
- 2018.05.01
- 保険金と税金《その2》
- 2017.10.11
- 保険金と税金《その1》
- 2017.07.12
- 法定相続情報証明制度
- 2017.06.05
- 国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し
- 2017.03.31
- 贈与したはずが相続財産に!?
- 2016.12.19
- 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』
- 2016.10.07
- みなし相続財産とは?